プレママも心配!妊娠と歯科の関係と赤ちゃんへの影響を知りましょう
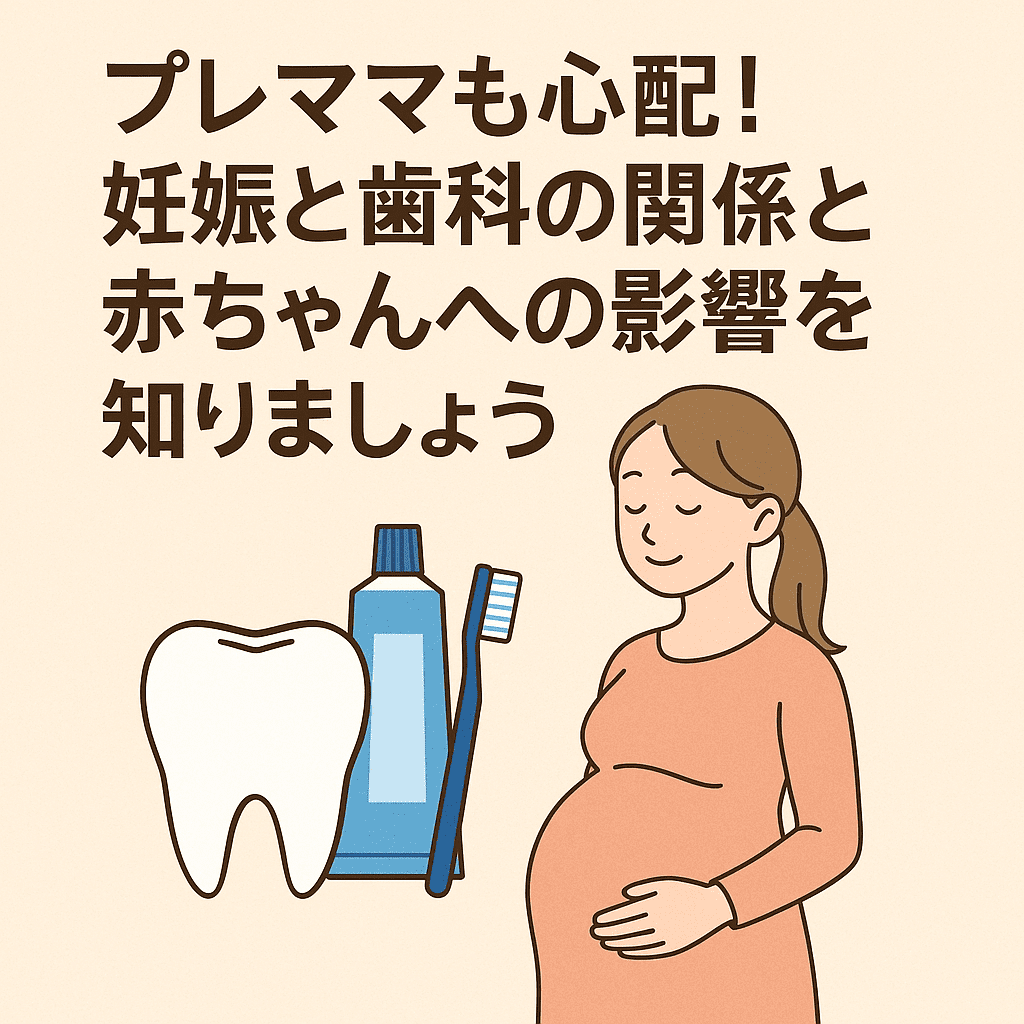
妊娠されると幸せな気持ちでいっぱいだと思います。
しかしその気持ちに反して、つわりや様々な体調の変化につらさを感じている方も多くいらっしゃいます。
風邪を引いていなくても具合が悪く熱っぽかったり、味覚や食の好みが変わったり、精神的な面でも不安定に陥りやすくなります。
見た目だけではなく様々な変化がある妊娠ですがお口の中の変化も大きく、また赤ちゃんへの影響もありますので今回は妊娠と歯科の関係についてお話ししたいと思います。
1、妊娠中の母体の変化
妊娠は最終月経開始日からカウントされて15週(4か月)までを妊娠初期、16〜27週(5〜7か月)を妊娠中期、28週(8か月)以降を妊娠後期と分類します。
妊娠初期(〜15週頃)は妊娠の発覚、つわりによる体調不良、喜びと不安の相反する感情を持つ事でのストレスを感じている事があります。
また仕事をしている方であれば職場への影響や、上のお子さんがいる方は子育てや家事をしながらの負担もあり精神的にも肉体的にも大変に感じている方も多いでしょう。
つわりと言っても気持ち悪くなって吐いてしまう『吐きづわり』だけではなく、何か食べていないと気持ちが悪くなるような『食べづわり』タイプもあります。
つわりが悪化し脱水症状や体重の大幅な減少があると日常生活が正常に送れなくなり『妊娠悪阻』と呼ばれる状態になります。
妊娠中期では身体がホルモンの変化に慣れてくるため体調も徐々に安定してくる方も多くなります。
この頃になると胎動を感じたり、エコーでの胎児の形がわかってきたりと赤ちゃんの存在を実感できる時期になります。
妊娠中の歯科治療は安定期と言われる妊娠中期に受診する事をお勧めしています。
6か月目の20週辺りから妊娠高血圧症候群の診断をされている方も増えてきます。
妊娠高血圧症候群は妊婦さんの約5%に見られるといいます。
原因は不明ですが、初産婦、多胎妊婦、もともと高血圧や血管の病気がある方、前回の妊娠で妊娠高血圧症候群と診断された方に多く見られる傾向があります。
また15歳以下、35歳以上の妊婦さんにも多く見られます。
妊娠後期になると子宮や赤ちゃんも急激に大きくなり始め内臓を圧迫したり、寝にくくなったり、便秘に悩まされる方も多くなります。
妊娠後期になると胎盤ホルモンの影響でインスリン抵抗性が高まり、血糖値が上がりやすくなります。そのため妊娠糖尿病はこの頃に多く発症が認められます。
妊婦さんの7〜9%に発症すると言われており、血糖値の上昇は胎児にも影響を及ぼし母子ともに様々な合併症を引き起こします。
例えばお母さんは網膜症や腎症、羊水の異常、妊娠高血圧症候群などがあります。
赤ちゃんでは流産、巨大児、心臓の肥大、低血糖、多血症、電解質の異常、黄疸、胎児死亡などの合併症があります。
妊娠も期間によって様々なリスクや変化があります。
そのため歯科治療に受診されてた方でも都度体調を確認し、変化があった場合はそれに応じた治療を選択することも必要になります。
2、妊娠によるお口の中の変化
妊娠をすると嘔吐を伴うつわりや、嗜好品の変化により唾液の酸性度に変化が現れます。
私も一人目の妊娠ではトウキビ茶ばかり飲んでいましたが、二人目の妊娠ではメロンソーダが美味しく感じていました。
この様に同じ妊娠でも1回目と2回目でも全く違った嗜好になる事もあります。
メロンソーダのように甘い物を頻繁に飲んでいたり、嘔吐を繰り返しているとお口の中は酸性に傾き、歯のエナメル質が弱くなる可能性があります。
また妊娠糖尿病の方は一回に摂取する食事を少なく、回数を増やすことで血糖値の上昇をコントロールしている事もあるため、口腔内環境は悪くなる傾向にあります。
またつわりにより、歯磨き粉の味や歯ブラシ自体が困難になる方もいます。
妊娠により唾液の分泌が減少する方もいます。
お口の中がネバネバすると思う方はそのせいかも知れません。
唾液が減少すると口腔内の細菌が増えやすく、虫歯や歯周病が進行しやすくなります。
また免疫力の低下から口内炎や、口角炎を起こしやすくもなります。
3、女性ホルモンと歯周病
様々な変化のある妊娠期ですが適切なプラークコントロールで歯肉の炎症は改善できます。
妊娠すると女性ホルモンの増加に伴い、非妊娠時と比べると歯茎の隙間にある滲出液の中の女性ホルモンは10〜1,000倍にも増えます。
この女性ホルモンを栄養素として利用する歯周病菌がいます。
そのため歯肉に炎症を起こしやすくなり歯肉炎、歯周炎に影響を及ぼすのです。
妊娠関連性歯肉炎・歯周炎の他に、妊娠性エプーリスという良性の歯肉のしこりの様な腫れも見られます。
妊婦さんの1〜5%に見られるといいます。
ただこれは出産後に消失する事が多いので経過観察をしていく事が多いです。
定期的に受診して頂き状態によっては外科処置も検討します。
もし歯茎に腫れが見られた場合、自己判断せず歯科を受診して判断を仰ぎましょう。
4、歯周病が原因になり得るトラブル
歯周病にかかっている妊婦さんは子宮収縮作用のある物質(PGE2:プロスタグランジンE2、炎症性サイトカイン)の血中濃度が高まります。
特にPGE2は陣痛促進剤としても使われており、強い子宮収縮を促します。
ですので安定期に入り通院が可能になったら、早産や低体重児出産のリスクを下げるために一度しっかりお口の中に炎症がないか確認してもらいましょう。
5、妊娠中の口腔ケア
前にもお伝えしましたが、妊娠中は体調の変化や嗜好の変化、唾液の変化などでお口の中のケアが疎かになりがちです。
私も歯科衛生士でありながら妊娠中は口腔ケアを頑張らなければと理解していても、奥歯や舌側の歯磨きが気持ち悪くなってしまい数ヶ月もの間、不十分なブラッシングを行なっていました。
その結果、歯磨きをすると血が出やすくなったり歯茎がじんわり痛む事もありました。
辛い時に頑張って磨くのはストレスになってしまいます。
多くの妊婦さんに見られる正常な反応ですので、無理せずできる範囲で行いましょう。
辛い時の口腔ケアのコツとして、
①食後はすぐにお水でブクブクうがいをして細菌の栄養になるものを少しでも取り除きましょう。
平気であれば洗口液を使うのもオススメです。
②お口の中が過敏で触れると吐き気を催しやすい時は子供用やワンタフトブラシというものを使ってみましょう。
③味が平気であればキシリトールガムやタブレットを摂取してみましょう。
④気分が良い時間が短い時は少しでも落ち着いている時に磨けるように家の活動範囲の目のつく所、手が届きやすい所に歯ブラシを置いておくのもいいでしょう。
6、虫歯菌の母子伝播
虫歯を作る細菌はたくさんあります。
免疫に良いとされる乳酸菌も実は酸を生み出し歯を溶かすものもあります。
そして様々な細菌は産道を通って生まれてくる時に感染が起こると言われています。
ですので、このたくさんの細菌を一種類もお口の中に居させないというのは不可能です。
ただ虫歯を作る細菌の中でも有名なストレプトコッカス・ミュータンス(以下S.mutans)は生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には存在しないと言われています。
S.mutansはあるタイミングで感染が起こり棲み着くことで虫歯のリスクが上がります。
世界的に見ても母親からの感染がとても多いのです。
しかしどんなに気をつけて唾液が子供の口腔内に入らない様に気をつけていても難しい事もあります。
ただし口腔内にS.mutansが多く存在する人と、存在はしているが少ない人とでは子供の虫歯のリスクに差が出るという研究結果があります。
口腔内のS.mutansが多い母親の方は早期から虫歯菌が感染、繁殖し多く存在する事がわかっています。
つまり小さな段階で虫歯になりやすいのです。
椅子に一人で座り、お口を開けて治療する事が難しい年齢に虫歯ができると簡単に治療ができない事もあります。
ですので、小さなお子さんの虫歯リスクを上げないためにも、ご両親のお口の虫歯菌を増やさないための口腔ケアもとても重要なのです。
7、終わりに

妊娠期の様々な変化は妊婦さん本人も驚きや戸惑いが多くあります。
妊娠してから歯科治療をする場合、物によってはお薬が使えないために我慢をしてもらわなければならない事もあります。
妊娠前から定期検診でお口の中に大きな問題を残さない事もとても大切です。
そして体調が安定してきたら早めに歯科を受診して問題がないかチェックして行きましょう。
産後は睡眠をとる事もままならず育児に奮闘する事になります。
そうなるとまた歯科受診から足が遠のきかねません。
妊娠中に歯科受診して頂ければ、産後のお子さんの歯についての心配事について相談したり、情報を提供する事もできます。
お母さんが常に大きな問題がないようにすることもそうですが、そしてこれから妊娠を望まれて妊活を始める方は是非パートナーと一緒に歯科を受診しておく事をお勧めします。



