骨がなくなる!?歯周病と骨のメカニズム
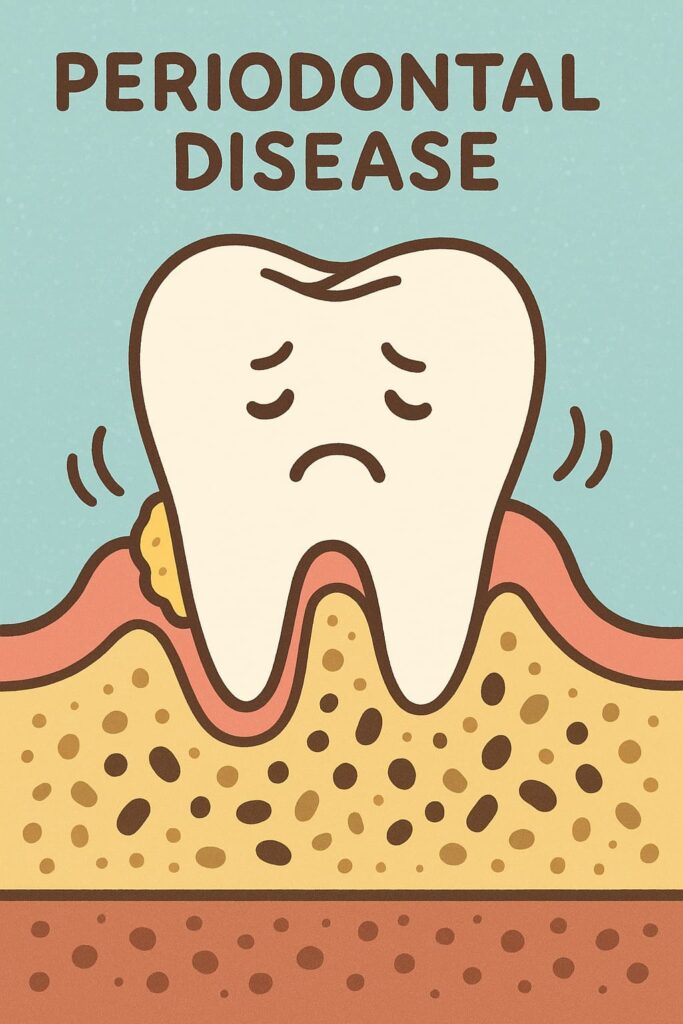
歯科の2大疾病は虫歯と歯周病です。
そのうち歯周病は骨がなくなる病気です。とても恐ろしいと思いませんか?
虫歯は虫歯菌の出す酸によって歯が溶かされて穴になっていきます。
歯周病も歯周病菌によって骨がなくなる、しかし正確には自身の細胞が骨を溶かしているといったら驚きませんか?
今回はそんな骨についてのお話です。
1.骨と歯の違い
骨と歯は似たようなものとお思いの方も多いと思います。
しかし骨と歯には大きな違いがあります。
骨は骨折してもまた修復されます。これは骨の新陳代謝によるものです。
骨は傷ついても傷ついた部分が壊され、新しく骨が造られます。これを骨のリモデリングと言います。
このリモデリングは様々な因子によって制御されていますが、骨粗鬆症や糖尿病などで骨の代謝が制御できなくなると上手く骨の修復が出来なくなります。
正常な骨の代謝があるお陰で抜歯後の傷が治ったり、インプラント治療や、矯正治療が成り立っています。
さらに骨の構造を詳しくみていきます。
骨は主にコラーゲン(タンパク質)とカルシウムやリンで出来ています。コラーゲンを含んでいることで骨はしなやかさがあります。反対にカルシウムやリンで硬さを維持しています。
極々細いコラーゲンの枠の中にカルシウムが詰まっているようなイメージです。その細い通路を骨を作る細胞(骨芽細胞と言います)と骨を壊す細胞(破骨細胞と言います)が行き来して骨のリモデリングに携わっています。
これに対して歯は自身で修復することがありません。歯の中の神経を守るため象牙質を造ることはありますがごく僅かです。エナメル質の再生はありません。ですのでしっかり管理して守る必要があるのです。
また歯が埋まっている骨(歯槽骨と言います)は上顎と下顎とでも硬さが違います。上顎は少し柔らかく、下顎は硬く出来ています。
そして骨は表面に皮質骨、内部が海綿骨という部分に分けられます。皮質骨は密で硬く、海面骨はスポンジ状で空洞があります。その空洞には血管が通っており栄養供給がなされています。
2.身体を支えカルシウムも貯蔵する骨
骨の役割と言えば身体を支える事、そして肺などの臓器を守る事が頭に浮かぶと思います。
しかし骨の役割はそれだけではありません。筋肉など細胞のカルシウムが不足すると骨から供給されるのです。
カルシウムは不足すると高血圧や動脈硬化、他にも筋肉活動の低下や脳の神経細胞の働きの低下も招きます。このカルシウムは体内で合成する事が出来ないので食事で取り入れる事が必要です。しかし食生活の乱れによりカルシウムが不足すると甲状腺からホルモンが出て破骨細胞が働き、骨を溶かし血中にカルシウムを送り込み不足分を補います。それが加速すると骨粗鬆症を生じるのです。骨粗鬆症も自身の持つ破骨細胞が徐々に自身の骨を溶かしてしまうことで起こる病気なのです。
歯周病も骨が溶かされ歯が抜けてしまう病気です。歯周病の病原菌は歯と歯茎の隙間に住み着き、炎症を起こしタンパク質や鉄など好物を摂取しながら温々生活をしています。しかし細菌がたくさんいると身体がそれらを排除して病を治そうとするのです。
3.骨のリモデリング
骨は新陳代謝を行なっており、その事をリモデリングと説明しました。
リモデリングには3つの細胞が携わっています。1つ目が破骨細胞、2つ目が骨芽細胞、3つ目が骨細胞です。まずはこれらの細胞について詳しく見ていきます。
①破骨細胞
簡単に言うと古くなったり、傷ついた骨を溶かす細胞です。
破骨細胞は酸やタンパク質分解酵素を放出し骨を溶かします。(これを骨吸収と言います)
細菌の侵入により炎症が起きると炎症を調節する為にタンパク質が生産されます。それが炎症性サイトカインと言うものです。そのサイトカインは免疫細胞を刺激して増殖を促します。
破骨細胞もその中の1つでサイトカインにより刺激を受け活性化されます。
歯周病はこれに加えて歯周病原菌の産生する内毒素(LPS:リポ多糖)、細菌の細胞壁の成分であるペプチドグリカン(PGN)、咬む力(咬合力)によって破骨細胞の活性化を促し、歯を支える骨を破壊していきます。
②骨芽細胞
骨芽細胞は破骨細胞に相反する細胞で新しく骨を生成する働きを持っています。(これを骨形成と言います)
骨芽細胞はコラーゲン繊維を作り、そこにカルシウムを沈着させて骨を作ります。
骨芽細胞の異常が病気を引き起こします。骨が脆くなる骨粗鬆症、そして歯周病もそのひとつです。
前述しましたが、炎症性サイトカインは破骨細胞を活性化させます。しかしそれだけではなく、骨芽細胞の分化や機能も妨げます。その結果、破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスが崩れて骨吸収が進行します。これが歯周病の骨が溶けるメカニズムです。
③骨細胞
骨細胞は骨を形成している細胞です。骨細胞同士は繋がりあっています。その繋がりでお互いに情報交換をしています。例えば力がかかっている部分にはもっと骨を強化するように指示を出します。
お口の中で言うと抜歯したところの骨は噛む力がかからなくなるので徐々に骨が痩せていきます。しかし欠損部分にインプラントを入れて噛めるようになると少しずつインプラントの周りに骨が添加されていきます。これが骨細胞の指示による破骨細胞と骨細胞のコントロールです。
4.骨を失わない為に
これまで骨の働きや新陳代謝について説明してきました。
私たちがお口の中の骨、歯を支える骨を失わないためにはどうしたら良いのでしょうか。
まず第一に細菌を減らす、増やさないことが大切です。そのため、私たち歯科医療従事者は日々の治療で治す事のみならず、お口の中の清掃状態を確認し、清掃方法のアドバイスを行い、ケアの届かないところはプロフェッショナルケアで細菌を取り除き、必要に応じて清掃しやすい環境作りを行っております。
3ヶ月に一度定期的なチェックを行なっている方でも問題が見つかる方がいらっしゃいます。
それは定期的なチェックだけではなく日々のホームケアが重要であることを示唆しています。
私たちがどんなに定期検診で口腔内をピカピカに綺麗にしてもその直後から歯磨きを怠れば2〜3日で細菌は歯に付着、増殖し炎症を引き起こしていきます。
もちろん完璧にお口の中を清掃することは私たち歯科医療従事者でも簡単なことではありません。ですのでまずは歯茎より上の歯の清掃を丁寧に行なっていただくように指導しています。その上で目に見えない歯茎の中や、普段の清掃用具が届かないところのお掃除を私たちが定期的にサポートさせていただき、細菌と炎症のコントロールを行うことが歯周病のコントロールの目標となっています。
また運動も大切な要素になってきます。適度な負荷をかけることは骨を丈夫にするためにとても重要です。
適度に負荷のかかっていない骨では骨細胞がスクレロスチンという物質を分泌します。
このスクレロスチンは骨吸収を促し、骨形成を抑制します。そのことで骨量を減少させるのです。
ですので歯周病による骨吸収を予防するためにはしっかりと噛むことも重要です。
硬いものを噛む事も推奨されますが、硬いものを噛むのが苦手な方には食材を少し大きくカットしてみることもお勧めします。その事によりしっかりと回数を噛むことも刺激になります。
時々患者さんで「もう歳だから骨も弱って痩せてきた」とおっしゃる方がいます。確かに加齢により骨芽細胞が減少することはあるようです。しかし中高年の方でもしっかり噛めることで骨量が増加したケースもあります。加齢がマイナスになる一方ではなく適度に刺激を与えて鍛えていくこともまだまだ可能なのです。
しかしそれだけではなく、骨を作る材料も必要です。カルシウムやリン、コラーゲンもしっかりと摂取していくことも大切です。加齢を原因に感じている方は、若い時のように栄養が十分に摂れていない方もいらっしゃると思います。そもそもの食事量が減少していれば若い時のように筋肉や骨も維持するのは困難ですし、その分の咀嚼回数も減少しています。摂取する栄養素はしっかり摂れるように効率よく食事内容を見直してみるのも良いかも知れません。
またカルシウムの吸収を良くするビタミンD(魚類や干し椎茸などに含まれる)や骨へのカルシウムの取り込みを促すビタミンK(納豆や緑黄色野菜、海藻類に含まれる)の摂取も忘れてはなりません。
牛乳だけじゃない!カルシウムを多く含む食品例
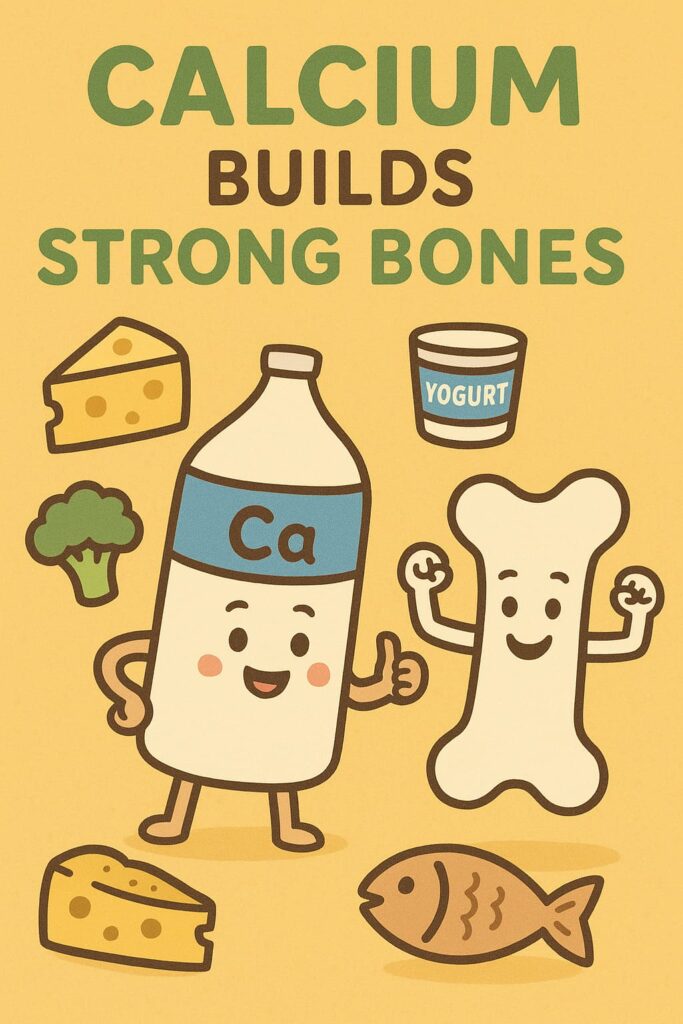
干しエビ バジル かたくちいわし ベーキングパウダー えんどう豆 こんにゃく
パルメザンチーズ ケール パセリ ごま ひじき 大豆 脱脂粉乳 わかめ 昆布
まとめ
終わりになりますが、私たちの身体は今こうしている間にも破骨細胞や骨芽細胞によってリニューアルされています。その働きのバランスが崩れることで病気になり骨が減ってしまうのです。
そして何より怖いのが痛みを伴わず知らぬ間に骨が減っていくと言う事です。
あれ?なんか歯が動く?物が挟まりやすくなった?歯ブラシで血が出やすいかな?は、身体からの危険信号かもしれません。少しでも早く骨が溶かされ歯が抜けてしまう事を阻止するためにも早めの受診と定期検診をお勧めします。



